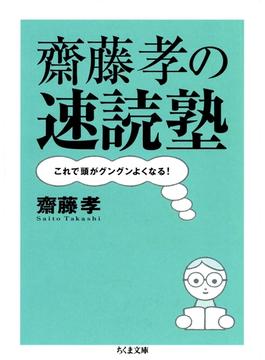1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:38mos - この投稿者のレビュー一覧を見る
良い!すごく為になりました!!速読の仕方より、本を読むという事の心得を教わりました。この本を読んで、読書に興味が持てました。
読書のヒントになる
2015/12/26 20:10
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:こばよ - この投稿者のレビュー一覧を見る
速読の方法には様々なものがあり、常に賛否両論があるます。この本で紹介されている速読法にも賛否両論あると思います。しかし、この本にはそれ以上に読む価値があります。他の速読本にはなかなか書かれていないことがあるからです
投稿元:
レビューを見る
本を読み終えた後、「要約できる」だけでなく、「新たな価値を付与して、オリジナルのアイデアや提案、見方が出せる力」を養うのが本書の目的。
最初から最後まで読まなければいけないという概念を捨て、必要な箇所に注力し、多くの本を読む時間に当てるためにどうするか。
少ない時間で多くの本を読むために私が実践すること
・読んだあと、書評を人に言う(→ブログに書く)
・読む締め切りを設定する
・いい引用文を見つける
・自分の興味のある本だけを読まないで、色々な分野の本を読む
本書の中で気になった・ためになったこと
・本を読むことは「視点移動」である
・多くの本を読むことで、より速く読めるようになる
投稿元:
レビューを見る
齋藤孝先生の著書は、これまでにもたくさん読んできたので、重なる部分が多いけれど、たまには、こうして先生の本を読んで、また背中を押してもらって、読書する気を起こしたいのです。
投稿元:
レビューを見る
●構成
第一講 何をどこまでめざせばいいのか:速読・多読の目標
第二講 勇気をもって飛ばし読み:「二割読書法」とは何か
第三講 誰でも今すぐできる速読術
第四講 速読上級者用プログラム
第五講 速読を生活にうまく組み込んでいく方法
--
私は、齋藤孝氏が好きではなかった。というより「○○力」という考え方やその言葉自体が嫌いだったし、今でも嫌いである。ついでに言うと、本書のタイトル(特に副題)も嫌いである。しかし、先日氏の書いた日本史を読んだことがきっかけで、氏の読書術に興味がわいた。それで本書を手に取った。
本書は速読のマニュアル本ではない。もちろん「技術面」にも触れているのだが、どちらかというと心がけ、「精神面」を重んじていると思う。まず、なぜ速読をするのか、速読で何が得られるのかという根源的なことから説く。
本書の方法のうち私にとって重要であり可能な方法として、「本の中でベスト3の箇所を選ぶ」「一文でいいから引用したい場所を決める」「抽象用語の理解が不可欠」がベスト3に入る。私は3色ボールペンで本に書き込みをするのはどうしても抵抗があり、2割読書法や右半分だけ読書法などは、ちょっとまだ私には難しい。ブックレビューは今やっているので、このまま続けたい。引用したい場所を選ぶなら、「なぜ引用部を記憶させるのかというと、本はその内容を引用できることに意味があるからです。読んだ本について要約して話すことができ、つねにそれを引用して魅力を語ることができれば、読んだ価値があります。」(p.90)を挙げる。引用することによって、その本の自分なりの最重要点が、後からコンパクトに確認できると思ったからである。
速読には当然技術面の訓練も必要である(フォトリーディングなど)が、それ以前に「何のために」をつねに意識した速読は、考えてみたら当たり前のことであるが私には、まさしく「目からうろこがおちる」そのものであった。それだけ日頃の読書が散漫であるということを考えされられた。
投稿元:
レビューを見る
最近こんな本ばっかり読んでる。速読についてあらゆる方法があるのを知ってるけど、今のところ一番役に立ってるのは、音読をしないこと、検索読み、飛ばし読みくらいだ。
斎藤孝さんの本は何冊も読んでるので、(相変わらず基本的に言ってることは同じ)すぐに読めた。
紹介されている方法は、具体的で実践的なので彼の主張を知らない人は一度読んで見るのもいいかもしれない。
二割読書法
時間を限定して読んでみる
タイトルからテーマを推測
引用ベスト3方式
本は単体でなく系譜で読め
同時並行で読み、読めないリスクを分散させよ
本は汚しながら読め(場所記憶)
本屋をトレーニングジムとして使え
目次を地図にしろ
息を吸ってはく間に一気に5行読み(高速黙読)
投稿元:
レビューを見る
本を1ページ1ページ理解しながら読むという概念を捨て、
要は肝心な部分を理解できそれを自分の言葉として引用出来ることが
「本を読む」ことの神髄だという。
☆30分で10冊読んで理解できる。
☆2割読書法で内容を8割理解
☆キーワード探し
☆本を読む事は「視点移動」である
☆1文だけでも引用出来れば勝ったも同然
投稿元:
レビューを見る
受身で読まず、概念を取り込む意識をもって読むことが大切。
同じ著者の本をたくさん読むことで著者のくせがわかり、読みやすくなるっていうのはナルホド。
でも2割読んで8割理解はホントか?
投稿元:
レビューを見る
実践書。本は2割読めばいい。1つでも引用出来るようにしようと思った。
あとは、もっと本に投資する気分にもなったかも。
投稿元:
レビューを見る
いつも思うんだが、速く読むのと、頭がよくなるのは関係ない気がする。それについてはどの本でも言及されていない。
投稿元:
レビューを見る
「齋藤孝の速読塾」5
著者 齋藤孝
出版 筑摩書房
p188より引用
“要するに、「速読・多読」するには、
つねに本に囲まれて暮らす環境をつくっておけ、
ということです。”
大学教授である著者による、
著者の専門分野を生かした速読法を伝授する一冊。
具体的で即実践できる方法が、
数多く紹介されています。
上記の引用は、
生活に読書を組み込む方法を紹介した章の一文。
このすぐ後部屋が狭くなるより頭が良くなる方が大事、
と書かれていますが、
なかなか部屋のスペースを自分の思いとおりに出来る人は、
多くないのではないでしょうか。
今よりも読書を深く広く楽しみたい方に。
ーーーーー
投稿元:
レビューを見る
速読についてよくまとめられた本だと思う。要点のみを読み解くなど、本を読む目的を忠実に遂行する方法が斬新だった。
投稿元:
レビューを見る
“塾”というだけあって、5回の講義(章)に参加して学ぶような形式になっています。とても読みやすい本です。
速く本を読むためだけの速読術ではありません。速読により多読が可能になり、その事による効用を示すことで本を読むことの大切さを教えています。
”Aレベルの理解力とは、新たな価値を付与して、オリジナルのアイデアや提案、見方が出せる力です。”(26ページ)
とするAレベルの理解力を得るための読書術を説いています。
日常的には、会議で配られた資料に目を通して、内容を早く理解する方法にも繋がります。
http://muragon.boo.jp/blog1/2011/07/14_2126.html
投稿元:
レビューを見る
本を読む意味は全部読み切る事ではなく、心に残る一文に出会い、自分オリジナルの言葉や経験と共に語れる事である。読んだ後にそれを誰かに発信する事により、洗練されていく。また納期を決める事により、速く集中して読む事が出来る。
自己満読書になってた事に気づかされた一冊。ブクログでレビューを書きたいと思ったきっかけの本です。
投稿元:
レビューを見る
読書がとても身近に感じられるようになった。
一般的に、本や読書に対して
・一言一句丁寧に読まなければならない
・本は大切に扱わなければならない
など、固いイメージがあると思うが、
(少なくとも私は、そう思っていた)
この本はそんなイメージを完璧に打ち壊してくれた。
本当に大事な二割だけ読めばいい。
適当に飛ばし読みすればいい。
ながら読みすればいい。
こんなこと、すぐに気づけるような気がするのだが、
心のどこかで、本に対して、一段上の扱いをしていたのだ。
そんな負の偏見を、この本がきれいさっぱり取り除いてくれた!
読書って、もっと気楽にやっていいものなんです。
これからはもっと手軽に、速読・多読を実践していきます。